管理人の独断と偏見 |
記事に不都合などありましたら、ご一報ください。
|
| HOME|テニス部紹介|現役部員の戦績|定期戦・対抗戦記録|管理人の独断と偏見|OB会(名簿・行事)|お役立ちリンク集|愛媛大学テニス部掲示板|愛媛大学テニス部(おまけのページ) |
 |
 全日本大学対抗テニス王座戦観戦記2004/10/16・17 全日本大学対抗テニス王座戦観戦記2004/10/16・17 |
 |
************************* * <<< 2005年度 報告 >>> * ************************* 2回生の三木昭範主将と八木祐介くん、1回生の水木舞さんから王座戦観戦のレポートが届きましたので紹介します。尚、2005年は観戦初日は雨天のため、順延となり、急遽名古屋で開催されている全日本ベテランを数試合観戦しました。王座戦の観戦は準決勝のみでしたが、多くの観客、また各校のOB、運営にあたる東海学生テニス連盟などにぎやかでした。さて、原稿は寄稿者の意思を尊重し原文のまま掲載します。(by 管理人) *--<三木昭範>----------------------------------* 全国王座を見ていろいろなことを感じることができました。残念ながら見学初日は雨で中止となってしまいましたが、2日目に準決勝を見ることができました。その日行われていたのは、近畿対法政、早大対関学で、早大が今年強いと聞いたので早大対関学の試合を中心に見ました。はじめセンターコートで行われていたダブルス2の試合を見ていましたが全然自分たちのテニスと違っていました。ものすごく丁寧で、サーブは速さよりコースと深さを、ファーストボレーを深くにきっちりと、リターンを返すというダブルスの基本がしっかりとできていると感じました。さら に自分たちのテニスと違うと思ったのはボールへの執着心が全然違っていることだと思います。相手がポーチに出ようとドロップ・スマッシュを打とうと拾える範囲のものは絶対に相手のコートに返すというような気迫が伝わってきました。これはシングルスの試合を見ているときにも感じました。そしてそのねばりからポイントにつながり、ゲームを取ることににつながり、試合の流れ自体も左右していたような気がしました。彼らはそれだけ1球の大切さを知っているのだと思います。またどの選手を見てもバランスがすごくいいと感じました。左右に振られているような 場面でも打つときにはしっかりとした体勢で入っていて次の動きにスムーズに入れていました。しかもそれがシングルスのファイナルセットに入ってもバランスは崩れずしっかりと打てていました。これは足腰を鍛えると同時に体力も相当鍛えてあるのだと感じました。彼らと自分たちと差があるのはこういう基本的なことに差があるのだと思います。技術云々ではなく基礎というものを鍛えていく必要があるということを改めて認識させられました。 試合を行っているプレーヤー以外にも勉強になったところがありました。1つ目はボーラーについてです。1コートにそれそれの大学から1名ずつ選手がボーラーに入っていましたが、どちらもとにかく速くまさに全力疾走という感じで、相手校のボーラーに取らせまいとボーラー同士で試合をしているかのように感じるくらい印象的でした。2つ目は応援についてです。早大は伝統を重んじていて正々堂々をモットーとしているためチェンジコート間の応援などはなかったが、どちらも毎ポイントごとに選手に声をかけていて周りから選手を盛り上げていくような雰囲気が あってすごくいいと思いました。どちらも選手をよりよい状態でプレーさせてあげるために必要なことであると思うので自分たちもしっかりしていきたいと思います。 今回の見学でここに書いたことだけでなく本当にいろいろなことを勉強することができました。キャプテンとして今回の体験を次の王座に活かしていけるよう努力していきたいと思います。今回の費用を出していただいたOBの方々本当にありがとうございました。 *--<八木祐介>----------------------------------* 去年の全日王座を見てから一年が過ぎ、今回王座を見に行く前に今年は"どこでどんなショットを打つか"を見ようと思っていました。どこに打って攻めるのか、どこに打って相手の攻撃をしのぐのかなどを中心に試合を見ました。もっと具体的にいうと、スライスをいつ、どう使うか、前へ出るタイミング、サービス、リターンのコース、ダブルスでのロブのあげる高さ、軌道、コースなどです。高いレベルにいる人達と私たち愛大の部員ではショットの質の差も多少ありますが、どこに打つか、攻め方、守り方など試合での展開力の差の方が大きいと思いました。だから私は今回学んだ攻め方、守り方などをほかの部員にも伝えて、みんなで来年こそ二部昇格を狙います。最後になりましたが経費を出してくださったOB会の皆様、二日間面倒をみてくださった華谷さん、良い経験をさせていただき本当にありがとうございました。 *--<水木 舞>----------------------------------* 10月15、16日に王座を見に行った。 1日目は、雨天のため試合自体は中止になったが、小雨だったため各学校練習をしていた。その内容は、ストロークラリーやボレーストロークなど、普段自分たちがやっていることとほとんど一緒だった。同じ練習内容のはずなのに、どこか違って見えた。「これが同じ大学生、同じ女子なのか!?」と思った。ボールの速さ、フットワークが良さなど、とにかくどのコートの選手を見ても軸がしっかりとしていてどのボールに対しても、同じ打点で打っていた。技術面以外にも、ボール1球1球を大事に打っているところや、コートで打っている選手以外の動きなど、コート内には無駄がなかった。練習風景を見たのはほんの数分の間だったけれど、様々な面で勉強になった。 2日目は、準決勝が行われた。私は相愛と早稲田の試合を見た。ダブルスは後衛がとにかくつないで甘くなったところを前衛が決めるという、まさに基本的なダブルスの形だった。どちらも隙がなく、ちょっとでも形が崩れたり、空いたところがあったら、すかさずそこをつかれて決められるといった感じだった。シングルスもただボール速いだけではなく、ちゃんとコースをついていて、あまくなったところを打ち込んで決めるという感じで、焦りがなく無理のない試合だった。レベルの差に関係無く、どの選手も1ポイント1ポイントあきらめずにボールに食らいついていったり、自分の得意のショットはきちんと決めていて簡単なミスも無く、どの選手も自分のベストを尽くしているように見えた。どの試合でも決めたときはすごく喜んで自分たちを盛り上げ、決められたとしてもすぐに切り替えて次のポイントに引きずらないようにしていた。周りの応援もとても良くて、みんながそのコートで戦っているかのように、チーム一丸となって試合を盛り上げていた。 試合で簡単なミスをしないとか、声を出して応援をするとかは普段の練習からそういったことを意識しているからこそ、いざ試合になったときに出来るのだと思う。強い学校はきっと試合以外のところでもしっかりとしている。何かオーラが違うと思った。自分たちにすごく自信を持っている風に見えた。歩き方もすごく堂々としていてすごくかっこよかった。今回王座を見に行っていろんなことを学んだ。その学んだことをこれからの練習に生かして今より上を目指していきたい。 私にこんないい機会をあたえてくださった華谷さんをはじめ、OBの皆さん本当にありがとうございました。 ************************* * <<< 2004年度 報告 >>> * ************************* 1回生2名より全日本大学対抗テニス王座戦観戦のレポートが寄せられておりますので紹介します。現在は男子3部、女子2部ですが今後のテニス部を1部昇格そして全国へ出場することを意識して、現状打破の機会を持とうということから実現しました。尚、寄稿者の意思を尊重し原文のまま掲載いたします。 *--<八木祐介>----------------------------------* ぼくたちは華谷さん一家にお世話になり、王座の全国大会を見に行くことができました。会場について最初に見たものは1、2回戦のスコアが書かれていたトーナメント表で、そこにはぼくたちの地区の代表、松山大学が愛知工業大学に4−5で初戦敗退という結果が書かれていました。そして、その愛知工業大学が第1シードの近畿大学に0−9で敗れていました。ぼくは今まで全国大会で上のほうのレベルの人たちは球のスピードはものすごい速さだと思っていたので、トーナメント表を見てその思いが強くなりました。しかし、その後すぐに試合を見ると、ぼくたち愛媛大学の部員にも出せないスピードではないことに驚きました。 1日目、準決勝が行われていて、近大(注:近畿大学)と第4シードの早大(注:早稲田大学)の対戦を見ることにしました。サーブの打ち方、ポイント間の時間の使い方、行動、リターンの立ち位置、ボールの運び、その他いろいろなところを観察しました。 試合中、試合後の審判への態度もまわりや観客に悪いイメージを与える学校も良いイメージを与える学校もあり、プレイ以外のところも大切だと思いました。 2日目、華谷さんのアドバイスで試合前のアップの方法を見ました。アップはぼくたちがしているアップとは特に違った様子はありませんでした。ぼくたち愛大生と全国大会に出ている人たちを比べてはっきり違う点は技術は別として、全国大会に出ている人たちのほうが1ポイントを大切にしているなと感じました。 ポイントをとると大きな声を発し、ガッツポーズをして自分を盛り上げさらにいい状態にもっていこうとしていました。それをさらに応援の人たちが選手を盛り上げ選手と応援が一丸となって試合をしていました。 今回の王座の全国大会を見にきて学ぶことは山ほどありました。それを自分だけが活かすのではなく他の見にいけなかった部員にも伝えて次の王座に向けてがんばっていこうと思います。良い体験をさせていただき華谷さん一家、OB会のみなさんありがとうございました。 *--<新宅弘幸>----------------------------------* まず、ダブルスは流れの変化が多く、決められて変わる流れよりもミスでの流れの変化が多いと感じた。特に同じミスをつづけることで流れが一気に悪くなりミスをしたペアの雰囲気も悪くなっていた。しかし次のゲームではしっかりきりかえていることがすごかった。 ベンチコーチはミスをしたときや決められたときよりも、決めたときに何かメモのようなことをしていたので、おそらくミスの追及などをするのではなく、いいかたちでとれたポイントで2人をはげましたりしていたのではないかと思えた。ポイントのとり方や、ミスになるときなどは自分たちとあまり変わらないと思ったが、自分たちと違うところは簡単なミスや絶対決められる場面でのミスが非常に少なく、決められそうでもあきらめることはなく、決めるほうも常にボールが返ってくると思いながら打っているため、返ってきてもあせることなくプレーしていることです。こういうところは今後の自分たちの練習の中で常に意識して練習することができればいいです。 彼らのプレーは一番得意なショットで勝負していることが明らかだった。相手にやりにくいようにすることより自分たちがやりやすいような陣形をとっているように感じられた。試合がすすむにつれて調子の悪いほうにボールをあつめたり、体勢が悪い方に徹底的にねらったりするようなことが多くなった。 シングルスはダブルスほど流れの変化はないように感じられた。よほど力の差がない限り一方的な試合はなかった。クロスラリーからストレートに切り返す展開がほとんどで、そのラリー中も得意なほうにまわりこんでいた。まずはねばって、あまい球などが来るまで無理せず、しっかりつなぐことはすごかった。相手のマッチポイントでも何も変わらず打て、自分のマッチポイントでもあせることなく同じプレーをして、最後まで気をぬくことなくプレーできる精神的な強さが自分との大きな差だと感じた。 王座の試合を見て、選手はみんな自信を持ってプレーしていると感じた。団体戦だから当たり前の事なんだと思うが、試合をあきらめることはなく、応援したくなくなるような試合もなかった。ひとつ気になったのは審判への抗議が多いことで、あまり見ていて良く感じなかった。 全体的にとても良い刺激を受けた。どうすれば彼らのプレーに近づけるか考えながら今後の練習を頑張っていきます。 最後に定期戦(注:医学部)があったのに行かせてくださったキャプテンや連れて行ってくださった華谷さん、お金を出していただいたOBの方々ありがとうございました。 *----------------------------------------------* |
 |
 この一球 この一球 |
「この一球」という言葉はテニスプレーヤーの間ではよく聞かれる言葉ですね。この言葉は早稲田大学出身で第1回全日本チャンピオンである福田雅之助氏の言葉です。尚、原文は早稲田大学庭球部のHPで確認してください。 規 この一球は絶対無二の一球なり されば身心を挙げて一打すべし この一球一打に技を磨き体力を 鍛え精神力を養うべきなり この一打に今の自己を発揮すべし これを庭球する心という 昭和四十九年六月 福田雅之助 |
 |
 団体戦におけるテニス 団体戦におけるテニス |
最近は団体戦を見ることが多い。 長女が中学生のときに校長先生の許可をいただいて、愛媛県代表として5名を引率し四国大会に参戦させてもらった。2年続けて3位だった。愛媛には中体連がなく、当然団体戦もない状況であったから、参加することに意味があったと認識している。その長女も大学生で王座に向けて練習していることと思う。 長男は高校生で選抜や総体で選手であったり、応援にまわったりで、団体戦を謳歌していると思う。選手として出たいと言う気持ちがあっても、当然実力の世界、皆に選手と認めてもらって、はじめて自分も自信をもったプレーとなる。 昨年来、県内大会はもとより高校選抜(北九州)、高校四国(高知)、高校総体(長崎)、国体(静岡)、おまけにスポレク、今年の3月には、全国高校選抜(福岡)、5月にはデビスカップ(大阪・靭)、日本がインドに勝った!74年ぶりに。6月には県高校総体、高校四国(砥部)を見た。 皆、自チームの誇りと名誉、時には国の威信をかけての戦いに武者震いしているかのように見えた。その思いや雰囲気は、見ているものに熱い情熱を思い起こさせるような衝撃を与えていた。 さて、団体戦はそのチームのカラーがそのまま出る。普段の礼節、練習態度、謙虚さ、情熱、闘争心、何をとってもである。 個人戦であれば、個人の資質、生地が主となるだろうが、団体戦では個が隠れてチームカラーが前面に出る。 さて、愛媛大学硬式庭球部のカラーはどう染まっているのだろうか? (by 管理人 2004/07/06) |
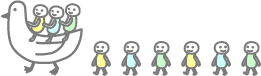 |
 |
 部誌 第32号(2004年版) 部誌 第32号(2004年版) |
本日(2004/7/15)部誌が届きました。現役諸君ご苦労様でした。また、OB会計係の渡邉さん、お疲れ様でした。 拝見すると、3回生の欄に4回生になった原稿、2回生に今年の現役、これも2年に1回の発刊となった影響でしょう。知りたい情報はOBにとっては色々あると思います。最近の大会結果かもしれませんし、また、それぞれのOBの最近の動向(テニス以外もあるでしょう)かもしれません。 何はともあれ、発刊にむけて編集責任者:近澤さんも大変だったと思いますが、この経験を卒業後の糧としてください。 内容については、OBや現役からの感想を、是非掲示板に投稿していただきたく思います。意見百出、それもよしと考えています。(by 管理人) |
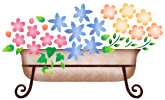 |
 |
 王座戦のルール 王座戦のルール |
関東学生のHPを見ていると、リーグ戦の規定などが冊子となりまとめられています。我々が学生の頃にもあったのかどうかはわかりません。現役諸君も存在を知っているのか、内容を理解しているのか、学生諸君に聞いてもいないのでどうかは分かりません。 ただ、こういう内容がしっかり明文化されているということは、中四国にも当然のことながらルールとして認知されていることだろうと推察致します。OBである我々も知っておかねば応援に行っても、選手諸君に不利な状況をもたらすかも知れませんので、一読しておくのがよいように思います。 |
 |
 リンク集 リンク集 |
 愛媛大学テニス部(おまけ) 愛媛大学テニス部(おまけ) |
このホームページでは記載できないことなどを管理人の勝手な思惑で書いています。また、フォトアルバムなどもあります。 |
 関東リーグ:冊子(規定集) 関東リーグ:冊子(規定集) |
関東学生テニス連盟作成のリーグ戦冊子に規約と注意事項が掲載されています。 |
 全日本学生選手権大会 全日本学生選手権大会 |
亜細亜大学テニス部コーチ森稔詞さんのレポートです。現役諸君是非一読を! |
 |
| HOME|テニス部紹介|現役部員の戦績|定期戦・対抗戦記録|管理人の独断と偏見|OB会(名簿・行事)|お役立ちリンク集|愛媛大学テニス部掲示板|愛媛大学テニス部(おまけのページ) |
|
